2008年9月26日(金)09:15
米投資銀行のゴールドマン・サックス(業界第1位)とモルガン・スタンレー(同2位)の2社は21日、そろって連邦準備制度理事会(FRB)の承認を得て、「銀行持ち株会社」(傘下に商業銀行を保有する持ち株会社)に転換する方針を打ち出した。
これにより、大企業や富豪しか相手にせず、超エスタブリッシュメントとでも呼ぶべき存在だった投資銀行業は、資本主義国の米国から消滅することになる。
そんな経済・産業史に残る“事件”を引き起こした真犯人は、いったい誰だったのだろうか。
投資銀行と言えば、中小の胡散臭いブローカレッジハウス(株式などの流通市場での売買仲介専業の証券会社)とは、一線を画す存在だ。業務や商品では、ブローカレッジだけでなく、M&A(企業の合併・買収)や債権を小口化・流動化する「証券化」、デリバティブ(金融派生商品)といったハイテクものを幅広く手掛けて、決算のたびに巨額の富を稼ぎ出してきた。社員は、ハーバードやウォートン、MITといった超一流のビジネススクールやロースクールの卒業生ばかり。特に「世界の工場」と称された自動車などの製造業が相次いで拠点を海外に移したり、凋落したりして米国で存在感を失ったあと、「バンカー」と呼ばれた投資銀行だけが資本主義国の象徴として米国民が世界に誇れる唯一の産業だったのだ。
こう考えると、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの決定は、メリル・リンチ(同3位)、ベアー・スターンズ(同5位)の身売りやリーマン・ブラザーズ(同4位)の破綻よりもずっと大きなニュースかもしれない。両社の転業は、映画にもなった金融の街・ウォール街を根城に、20世紀初頭から栄華を極めてきた投資銀行の歴史にピリオドを打つことになるからである。
米国では、今年に入ってすでに12の地銀が破綻した。中には、インディマックのように預金を引き出そうという人々の長蛇の列ができ、取り付け騒ぎと報じられたケースもあった。その一方で、全米最大の保険会社AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)もFRBの緊急支援を受けた。まさに「金融恐慌」の嵐が吹き荒れている。
日米のメディアは、この金融恐慌を、ゴールドマンやモルガンに銀行持ち株会社への転換を迫った主犯(金融恐慌主犯説)と報じている。銀行持ち株会社にはFRBから直接資金を取り入れられる利点があるからだ。だが、投資銀行が消滅に追い込まれた背景には、もっと根の深い政治的な理由があり、真犯人も別に存在すると言わざるを得ない。
PR
2008年9月16日(火)07:00
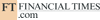
(フィナンシャル・タイムズ 2008年9月14日初出 翻訳gooニュース) ジョン・ギャッパー
リーマン・ブラザーズが前回、1984年にいったん破綻したときの顛末を、ケン・オーレッタが著書「ウォール街の欲望と栄光—リーマン・ブラザーズの崩壊」で書いている。この中で同銀のリチャード・ファルド氏は激しく、誇り高く内向的な、債券取引のトップとして登場する。内部抗争のせいで同社が身動きとれなくなっても、ファルド氏は売却の必要性を受け入れなかった。
1984年の当時、リーマンは結局アメリカン・エキスプレスに売却され、ファルド氏はその後、リーマンのCEOとなる。ファルド氏のもとでリーマンは1994年に分離独立し、以来、リーマンがゴールドマン・サックスなどのウォール街企業をしのぐことは決してないという懐疑的な業界予測をよそに、邁進を続けた。
リーマンが変身したのは、変身しなくてはならないとファルド氏が主張したからだ。ファルド氏は、チームワークの必要性を絶え間なく強調し、内部対立を排除していった。主力の債券取引のほか、資産管理やエクイティー部門を強化し、業務の幅を拡大した。
しかし実のところ、ファルド氏自身は全く変わっていなかった。それまでと全く同じ、暗く内向的で頑固で、リーマンに忠実。自分の会社を売るなどとんでもないと、売りたくないと頑なだった。そしてリーマンはここ半年、必死になって会社を建て直そうとしていたのだが、最後には結局、ファルド氏のプライドと頑固さが銀行再建の妨げとなってしまった。
ウォール街4位の銀行にまでリーマンを成長させたファルド氏は、受け入れがたきを受け入れられなかった。緊急に必要な資金を作るには、相当数の自社株を安価で売るか、資金運用部門を売却するしかなかった。しかしファルド氏はこのどちらにも、なかなか踏み切らなかったため、結局は間に合わなかった。
「ディック(リチャード)は売却に対して、病的な抵抗感があったのだと思う」 ある銀行マンはこう言う。リーマンの株価が下がり続け、その将来に対する不安が立ちこめるようになっても、ファルド氏はリーマンを帳簿価額よりも安く評価するような資本注入(たとえば韓国産業銀行から)はいっさい受け入れられないと拒否した。
そのような出資を受け入れてしまえば、リーマンの価値は実際にはわずかなものに過ぎないと認めてしまうことになる。そんなことになれば、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーやメリル・リンチに匹敵する存在になるまでリーマンを大きくしてきた、自分のこれまでの努力が全て水泡に帰してしまう。そんな展開は、ファルド氏にとって決して受け入れられるものではなかったのだ。
しかしファルド氏の失敗は、自分が好まない取引を拒否したことに留まらない。ここ1年、ウォール街に吹き荒れた信用収縮危機にどう対応すべきか、ファルド氏は目に見えて混乱し、曖昧な態度を取っていた。社内にも社外にも、明確なメッセージを発信できなかったことが、さらにリーマンを痛め付けた。
社内的には、今のこの金融危機が世界を大きく変えてしまった、その影響がいかに深刻かをはっきり認識するのが遅れた。昨年10月には、不動産開発業者ティシュマン・スパイヤーと共同で不動産会社アーチストン・スミスの買収をそのまま進めて、220億ドルを払っている。その2カ月前の8月時点でウォール街はすでに信用収縮の打撃を受けていたのに、リーマンはこの買収を敢行したのだ。
市場が危険な状態にある中、アーチストン・スミスのようなこうした取引のせいで、リーマンの不動産リスクは高まっていった。そしてリーマン社員によるとこの間、前社長で最高執行責任者(COO)のジョー・グレゴリーは前年の債券取引のリスク・プロファイルを引き下げようとしなかった。潜在的利益を手放したくなかったのだ。
今年6月、リーマンは3~5月期決算で28億ドルの赤字を計上し、60億ドルの緊急増資を実施したが、その頃にはもう事態は制御不能になっていた。ファルド氏はグレゴリー氏とエリック・キャラン最高財務責任者を解任したが、それでも秩序を回復させられなかった。「リーマンはあらゆる段階でことごとく遅れをとり、後手後手に回っていた」と、ある銀行関係者は言う。
この今年6月時点でファルド氏はついに社員に対して、会社はかなりひどい混乱状態にあると認めている。「5四半期にわたってまずい判断が続いた」と述べ、もっと積極的に立て直しを計るべきだったと語っている。この時点でリーマンに残されていた頼みの綱は、ファルド氏には好ましくない形で大量の資金を集めることしかなかった。
こうした状態で対外的には、リーマンが自分たちの救済策として何をするつもりなのか、不透明感が広がった。
韓国産業銀行(KDB)と交渉している情報が外にもれ、あるいはリーマンは資産運用部門ニューバーガー・バーマンを一部か全部、売却するのではないかという可能性も取りざたされた。
リーマンの破綻は金融市場にとって、そしてウォール街全体にとって、不安材料だ。またファルド氏によって揺るぎない愛社精神と仲間意識を叩き込まれた社員2万4000人にとっても、これは悲劇だ。社員の多くは、資産の大半をリーマン株で持っている。しかしそのリーマン株はもはやほとんど価値を失ってしまった。
ファルド氏にとっても、古典的なギリシャ悲劇的な意味で、これは悲劇だ。あまりにも自分の全てを、自分の人生と自分自身そのものを、この銀行に注ぎ込んできたせいで、その衰退を受け入れられなかったのだ。もっと早くに売りに出ていたら、リーマンは生き残ったかもしれない。けれどもファルド氏はプライドが高すぎた。思い上がりのあとに、破滅がやってきたのだ。
参考:
http://news.livedoor.com/article/detail/3290771/
東南アジア大丈夫か!?
ラオスで中国企業進出かぁ・・・・
数年前とはビエンチャンの様子も様変わりしてるのかなぁ。。。。
寂しいなあ。
また行きたい行きたいとは思いつつも、やはり簡単に時間はとれず
いけてない。
2年以内にまた行きたい!!!!
参考Gigazine:
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070828_underwear_ad/
そしてGigazineが引用していた元サイト(英語):
http://www.nuacco.com/2007/08/27/men-dont-want-to-look-at-naked-men/
男性下着の広告としてはすごく良いと思うんだけど?
まずインパクトあるっていうのが広告の第一要素だよね。
下着の臭いを嗅いでる構図もまた目を引く(笑)
なんで臭い?ってとこで。
まぁ、色んなものを連想させられるよね。
女性差別という事で今年は広告できないみたいだけど、
差別っていうのも難しいところだよね。
少なくともこの会社は、世界的に話題となった点で
広告と作った意味はあったと!
http://blog.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/129484
中国に限らず、世界各国色々なものが売られてますね。
しかしまた、この角もいかにも剥ぎ取ってきました!!と言わんばかりの形で
鎮座ましてますね・・・
私は割りと他の場所や異国に行っても、すぐ慣れてしまうのでぼーっとしてると
特に差異に気づかず過ごしてしまう。
だからなるべく旅行中は目を光らせては見るものの、疲れるので最後は
現地に同化します(笑)
比較文化論とか読んでみると、
何が良くて何が悪いのか、わからなくなってきます。
単なるお金儲けの為では話が違ってきますが、今回の場合はこれを売ることが
彼らの生活・生きる糧になるんですよね。。。。
難しいね。
今年の夏はまた中国行こうかな。
